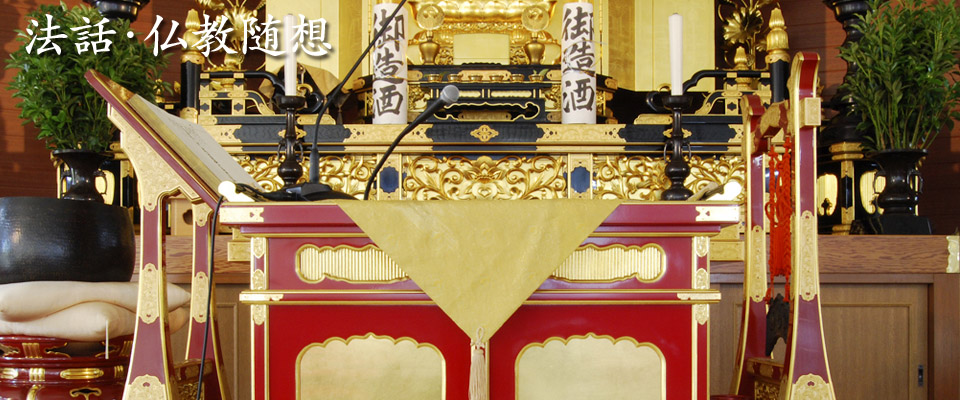『立正安国論』は日蓮大聖人が国家諫暁の書として著された、代表的な著述であることは広く知られています。四六駢儷体(しろくべんれいたい)という漢文の一手法が用いられ、対句により音読すると流麗な響きがあります。
文応元年七月一六日、大聖人はこの書を幕府に奏進して、唯一の正法である法華経に帰依すべきことを説かれました、ここに至った直接の機縁は、これより三年前、正嘉元年八月二十三日を中心とする、鎌倉大地震を体験されたことによるものでした。当時の史書『吾妻鏡』にも、
「大地震、音あり。神社仏閣一宇として全きことなし(中略)中下馬橋の辺、地裂け破れ、その中より火炎燃え出づ」(同年八月二三日条)
と、記されるほどの惨状でした。
この頃、鎌倉に庵室を構えていた大聖人は、地震後の変わり果てた光景をまざまざと御覧になられています。しかしこれは惨状の始まりと言うべき事態でした。十一月には同規模の大地震、翌二年八月一日には大暴風、同三年の大飢饉、翌正元年の大飢饉と大疫病の流行、翌二年は四季を通じての疫病流行と続きます。まさに『立正安国論』冒頭にある、
「牛馬巷に斃(たお)れ、骸骨(がいこつ)路に充てり。死を招くの輩既(すで)に大半に超え、之を悲しまざるの族敢へて一人も無し」
とあるのは決して誇張ではなく、現実そのままの描写でした。
驚いた朝廷・幕府は、全国の諸大寺院に災難退治の祈祷をなさしめるも、人々の悲惨な度合いは増すばかりです。
ここにおいて大聖人は、念仏や禅の教えに頼る当時の世相に原因があるとの思いを致され、その経証(経文上の証明)を得べく、岩本実相寺の一切経蔵に入られました。この時、実相寺・四十九院の学徒であった伯耆公(ほうきこう)こと日興上人が弟子入りを願い、久遠よりの師弟の因縁が開花したのも、むしろ自然の成り行きでした。
こうして、三災七難の由縁を説いた諸経の文証をもとに、世に行われている邪法邪義を捨てて「実乗の一善」、即ち法華経の肝要である南無妙法蓮華経に帰依することが、世を救う唯一の道であると説いた『立正安国論』は、文応元年七月十六日、幕府の要人宿屋左衛門入道を通じ、最明寺入道北条時頼に奏進されたのでした。他の御書には大聖人が直接時頼に会われたことも記され(故最明寺入道見参御書)、安国論の内容に、時頼も非常に関心を寄せていたことをうかがわせます。
さて『立正安国論』奏進当時、破折の対象に挙げられた念仏僧を中心に、大きな反発があり、松葉ヶ谷の法難を引き起こしています。さらに彼等は、讒言(ざんげん)を用いて北条氏の長老的存在であった極楽寺重時等を動かし、翌弘長元年五月には伊豆配流となりました。
これで安国論奏進による騒擾(そうじょう)は、終息したかに見えましたが、御歳四十七歳の文永五年閏一月、突如として蒙古国より牒状(ちょうじょう)が到来、日本へ服属を求めてきました。いわゆる大聖人が安国論に、近い将来他国侵逼と自界叛逆の二難があることを予証してより九箇年、このことが符号したことに世上は大騒ぎとなりました。大聖人は就任したばかりの執権北条時宗をはじめ幕府首脳や鎌倉諸大寺院に十一通御書を送り、安国論の内容を再考するよう厳しく求められました。
こうした事態の中で、大聖人の存在と安国論の内容は、日本国全体に大きくクローズアップされていったのです。
翌文永六年には蒙古より再度牒状が届けられました。この年の末頃、大聖人様が筆写された安国論が、富木常忍有縁の中山法華経寺に残され国宝に指定されています。その奧書に、
「此の書は徴(しるし)有る文なり。是偏に日蓮の力に非ず、法華経の真文の感応(かんのう)の致す所か」(平成新編御書四二〇㌻)
とあります。安国論の内容は、単に一個人の著述などではなく、法華経の意(こころ)を文字として顕したものであり、末法御本仏が示される世の指標であるとの深意がうかがえます。
このように推移する中で、大聖人の教えを求める人が鎌倉を中心に、次第に増えていったことは当然想像されます。しかしそれが、極楽寺良観をはじめとする他宗の僧や、平左衛門尉頼綱等、幕府内の権力者に危機感を懐かせ、文永八年九月十二日の竜口法難を迎えるのです。
それに続く佐渡配流は、当初は竜口での斬首をもくろんだ頼綱等が、果たせなかったことで急遽方針を転換した処断でした。
ところで「法華経の真文」とまで仰せられた安国論の予証が、再び現実となる事態を迎えます。いわゆる配流の翌年早々、執権時宗と六波羅探題の兄時輔(ときすけ)との間に内戦が起こっています。他国侵逼難に続く自界叛逆難の現証でした。この事は、蒙古再度の来襲を恐れる幕府にとって、大聖人様への扱いを再考せざるを得なくなりました。すなわち文永十一年春に、佐渡配流赦免の決定へとつながるのです。
鎌倉に戻られた大聖人に向かって、平頼綱は「蒙古は何時攻めて来るのか」と問うほど、すでに無視の出来ない存在でした。しかし頼綱の権力が、執権を凌ぐほど次第に強大になっていく中で、幕府は大聖人の忠告を顧みる余裕はなく、元弘三年の鎌倉幕府滅亡まで、走り続けざるを得なかったのです。